市町村は高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置の実施に努めることとされています。(災害対策基本法第8条第2項第15号)
東日本大震災や熊本地震をはじめ、近年の風水害、地震災害等においては、高齢者や障害のある方、妊産婦等に被害が集中する事例が多く見受けられることから全国的に災害時における要配慮者の避難支援体制の整備が課題となっています。
※要配慮者とは、具体的には次のような方々です。
・心身障害者(肢体不自由者、知的障害者、内部障害者、視覚・聴覚障害者)
・認知症や体力的に衰えのある高齢者
・日常的には健常者であっても理解力や判断力の乏しい乳幼児
・一時的な行動支障を負っている妊産婦(妊娠中かた概ね産後6か月)や傷病者
要配慮者は、一般の人々と同じような危険回避行動や避難行動を行うことが困難です。また、避難生活においても特段の配慮が必要となります。
また、災害時には誰もが要配慮者になる可能性があります。要配慮者にとって優しいまちは、誰にとっても優しく、災害に強いまちといえるでしょう。
京都市では、こういった方々を支援するための様々な対策を行っています。
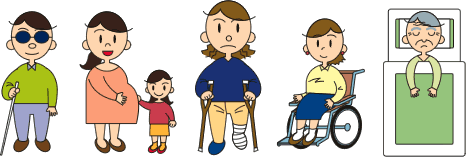
京都市福祉避難所について
福祉避難所とは、避難生活において一定の配慮を要する方を対象とする避難所のことです。
福祉避難所は、一般の避難所への避難後に、そのまま一般の避難所での生活を続けることが困難な方を対象とするため、二次避難所とも呼ばれています。
なお、本市では要配慮者が安心して避難生活を送ることができるよう、社会福祉施設等の福祉資源を活用した福祉避難所及び妊産婦等福祉避難所の事前指定を進めています。
〇福祉避難所の受け入れ対象者
高齢者や障害のある方、妊産婦(妊娠中から産後概ね6か月)など、避難生活において特別な配慮を必要とする方で、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の方が対象です。
京都市福祉避難所備蓄計画
福祉避難所の備蓄に当たっては、福祉避難所事前指定施設(以下「事前指定施設」という。)及び当該施設の運営法人に加え、関係団体の協力を得るとともに、事前指定施設に対する公的備蓄物資の配備の実効性を確保するための下位計画として、平成28年2月に、京都市福祉避難所備蓄計画を策定し、取組を進めているところです。
令和2年3月には、平成31年3月に改定された京都市備蓄計画の内容を踏まえ、福祉避難所備蓄計画を改定しました。
京都市福祉避難所運営ガイドラインの策定
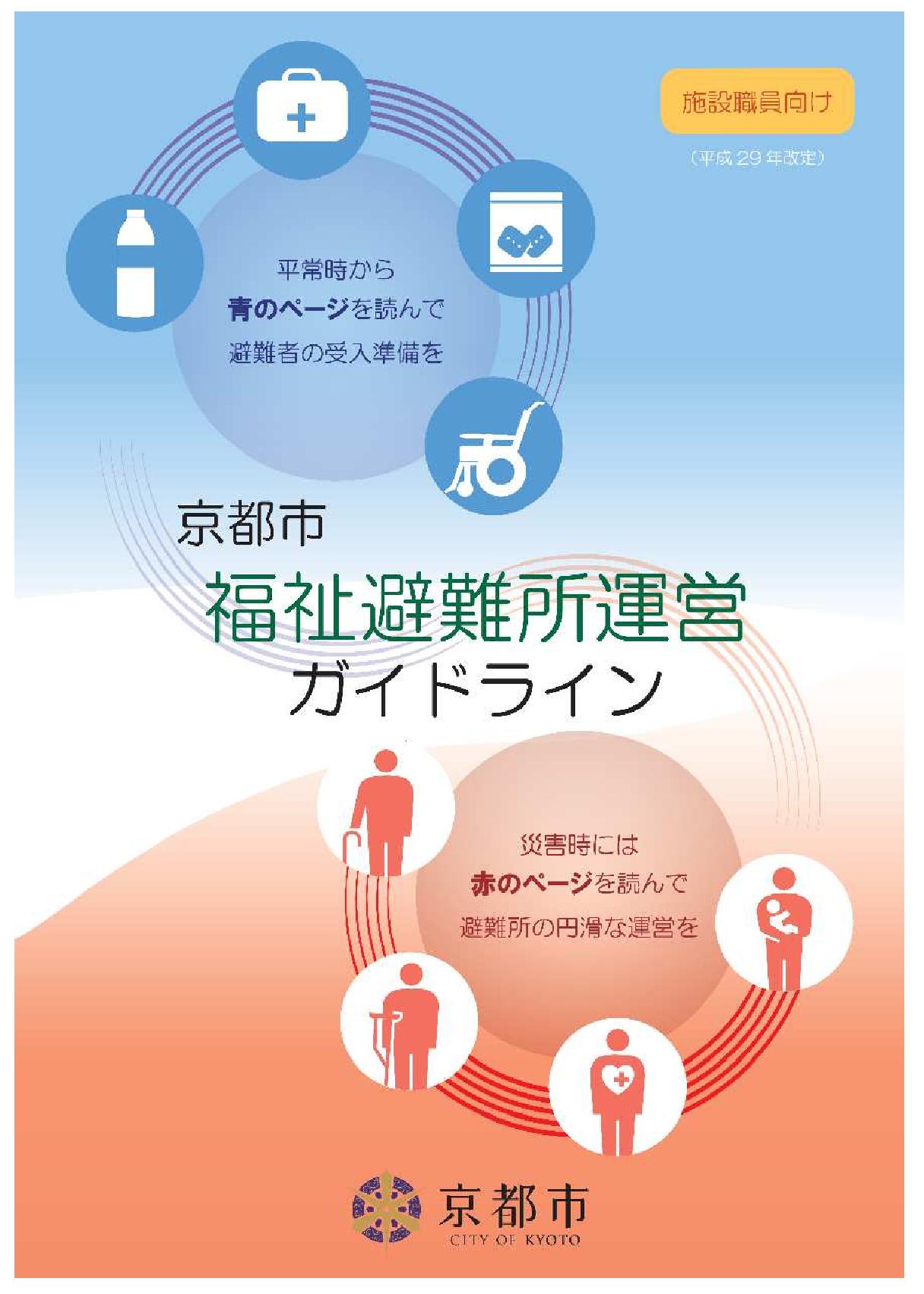
福祉避難所を運営する社会福祉施設等の職員の皆様のために、各福祉避難において策定する運営マニュアルの基本となるガイドラインを策定するとともに、地域住民の皆様に福祉避難所の取組を知っていただくために、パンフレットを作成しています。
- お問い合わせ
保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課
電話:075-222-3366
概要
平成25年3月、事前準備の推進を目的とした「平常時の取組」と、いざという時の福祉避難所運営に必要な「災害時の取組」で構成し,福祉避難所の事前準備及び開設から撤収までに必要な情報や取組内容を時系列でまとめ、施設職員向けマニュアルを作成していくために、「京都市福祉避難所運営ガイドライン」を策定しました。
平成29年4月には、「京都市福祉避難所移送対象者の選定方法及び受入調整等に関するガイドライン」及び「京都市福祉避難所備蓄計画」の策定を踏まえ、京都市福祉避難所運営ガイドラインを改定しました。
特徴
基本的な考え方
- 平常時
災害発生に備え日頃から事前準備を進める。 - 災害時
避難者にも役割を与え生きる意欲を失わせない。
介護予防に努め、避難者を寝たきりにさせない。
早期の通常運営回復を目指す(特に通所施設)。
開設時期
発災後、施設の安全点検や人員体制の確保等の準備を終え、受入体制が整った施設から順次、区役所・支所災害対策本部と調整の上、対象者の受入を開始することを基本としています。
設置期間
災害救助法では、福祉避難所の設置期間は、原則として災害発生の日から起算して7日以内となっていますが、過去の災害時の事例等から、7日以内で収束することが難しいため、一般の避難所と同様に、災害発生の日から概ね3週目以降に福祉避難所の撤収に入ることを想定しました。
その他
主に2色で構成し、平常時は青のページ、災害時は赤のページとし、各ページにインデックスを設けました。
主な内容
平常時の取組
福祉避難所の対象となる方、避難の流れ、災害発生時における職員の動きのモデルフロー図や京都市等の連絡調整体制に加え、「備えておくべきこと」として、職員の参集や役割分担等を定めたマニュアル等の整備、備蓄に関する事項、要配慮者の特性や配慮事項等について掲載しました。
災害時の取組
災害発生直後~3日後を「初動期」、3日~2週間程度を「展開期」、3週目以降を「安定期」及び「撤収期」と位置付け、それぞれの時点ごとの、京都市地域防災計画に基づく、区災害対策本部、市災害対策本部、福祉避難所の連絡体制フロー図や、福祉避難所の円滑な運営のために踏まえておくべきルール及びノウハウ等を掲載しました。
様式集
巻末に様式集を設け、平常時に、一定部数を複写し確保しておくこととしました。
地域における見守り活動促進事業
一人暮らしの高齢者や障害のある方などで、日常的な見守りを希望される方の住所・氏名・連絡先等の情報を記載した名簿を作成し、地域の関係機関(高齢サポート、民生児童委員、学区社会福祉協議会など)に貸し出すことにより、生活実態の把握や援助活動、情報の提供など、地域における日常的な見守り活動につなげていきます。
<対象となる方>
次に掲げる方のうち、個人情報を提供することに同意された在宅の方
1.65歳以上の要介護1・2、要支援1・2の単身世帯等の方
2.要介護3以上の方
3.身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定の単身世帯等の方
4.障害支援区分4以上の方
5.本市のあんしんネット119(緊急通報システム)を設置されている方
6.65歳以上の単身世帯の方
※1及び3の「等」とは、1~5の方のみで構成される世帯です。
1~5の方については、本市から個人情報の提供に係る意思確認を行い、不同意の意思を示した方以外の方です。
6の方は、本市に個人情報提供同意書を提出することが必要です。高齢サポートによる一人暮らし高齢者宅への訪問活動でご自宅を訪問した際にご説明します。
お問い合わせ
電話:075-222-3366
